政府、首相の関与否定に躍起 海水注入中断問題 過去の政府資料を訂正
2011.5.21 22:57 東京電力福島第1原発への海水注入が菅直人首相の「聞いていない」発言により中断したとされる問題で、政府は21日、打ち消しに躍起となった。
細野豪志首相補佐官は過去に発表した政府資料を都合良く訂正した上で「事実に基づかない」と反論したが、政府関係者の証言との矛盾がますます増えており、むしろ疑念は深まった。自民党は週明けから国会で徹底追及する構え。
海水注入一時中断「人災の面も」 自民・谷垣総裁
細野氏は21日夕、都内の東電本店で開かれた政府・東電統合対策室の記者会見で経緯を説明した。 それによると、首相は3月12日午後6時に始まった政府内協議で「海水注入で再臨界の危険性はないか」と聞いたところ、原子力安全委員会の班目春樹委員長が「危険性がある」と指摘したため、ホウ酸投入を含めた方法を検討した。
東電は午後7時4分から1号機でホウ酸を入れない「試験注入」を始めたが、官邸の指示を待つために同25分に注入を停止。首相が海水注入を指示したのは同55分だったとしている。
細野氏は、東電の試験注入について「原子力安全・保安院には口頭で連絡があったが、官邸には届かなかった。首相が激怒することもない。私が知ったのも10日ほど前で驚いた」と首相の関与を否定。過去に公表した政府資料に「午後6時の首相指示」との記載があることについては「『海江田万里経済産業相が東電に海水注入準備を進めるよう指示した』と記述するのが正確だった」と訂正した。 複数の政府筋によると、首相が海水注水について「聞いていない」と激怒したことは複数の政府関係者が記憶しており、斑目氏が「海水注入は再臨界の危険性がある」などと指摘した事実もないという。
この問題を受け、自民党の谷垣禎一総裁は21日、新潟市で「事態の処理を遅らせたとすれば人災という面が非常にある」と批判。同日夕、大島理森副総裁、石原伸晃幹事長らと党本部で協議し、週明けから原発事故の政府対応を国会で徹底追及する方針を決めた。
鳩山由紀夫前首相も北海道苫小牧市で、政府の事故対応を「事実が必ずしも国民に明らかにされていない。重く受け止めなければならない」と批判した。
3号機から海に20兆ベクレル流出、がれきは千ミリシーベルト
2011.5.21 11:48 福島第1原発3号機の取水口付近から高濃度の放射性物質(放射能)を含む水が海へ流出した問題で、東京電力は21日、海へ流出した放射性物質の総量は20兆ベクレルとの評価結果をまとめ、経済産業省原子力安全・保安院に報告したと発表した。 東電によると、3号機の立て坑の水位の変化などから、汚染水が流出していた期間は10日午前2時から11日午後7時までの約41時間と推定。流出量は当時の画像などから、毎時約6トン、計約250トンと試算した。
また東電は、3号機原子炉建屋の南側で、毎時千ミリシーベルトの高い放射線量のがれきが見つかったと発表した。これまでで見つかったがれきで線量は最大。 がれきは3号機原子炉建屋とコンクリートポンプ車の間にあり、20日に見つかった。コンクリート片のようなものと紙状のものがあるという。周辺の線量は毎時40ミリシーベルトで、東電は付近に作業員が立ち入らないよう措置をとった。 3号機周辺では4月20日にも、毎時900ミリシーベルトのがれきが見つかっている。
班目氏が政府発表に「名誉毀損だ」と反発 政府は「再臨界の危険」発言を訂正
2011.5.22 20:42 内閣府原子力安全委員会の班目(まだらめ)春樹委員長は22日、東京電力福島第1原子力発電所への海水注入が菅直人首相の発言を契機に中断したとされる問題で、政府・東電統合対策室が「班目氏が首相に『海水注入の場合、再臨界の危険がある』と述べた」と発表したことに反発し、福山哲郎官房副長官に文言の訂正を求めた。政府は班目氏の発言は「そういう(再臨界の)可能性はゼロではない」だったと訂正した。
班目氏が官邸・東電側の説明の根幹を否定し、政府が追認したことで、政府発表の信憑(しんぴょう)性に疑問符がついた。
海水注水がなぜ中断したのかは、明らかにされておらず、首相の発言が事態を悪化させた可能性は残っている。混乱する政府の対応は、23日からの国会審議で問題になりそうだ。 班目氏は22日、内閣府で記者団に「そんなことを言ったら私の原子力専門家の生命は終わりだ。名誉毀損(きそん)で冗談ではない」と強調。さらに「(真水を)海水に替えたら不純物が混ざるから、むしろ臨界の可能性は下がる」と説明していた。
一方、細野豪志首相補佐官は22日のフジテレビ「新報道2001」で「『真水から海水に替わるわけだから何か影響はないのかしっかり検討するように』という首相の指示は出た」と述べた上で、海水注入による再臨界の危険性には「班目氏自身がそう言ったと記憶がある」と語っていた。
枝野幸男官房長官は青森県三沢市で記者団に「東電がやっていることを(政府が)止めたことは一度も承知していない」と政府の指示を否定した。
細野補佐官「首相は再臨界を心配していた」
2011.5.22 20:49
22日にフジテレビ系で放送された「新報道2001」では、東京電力福島第1原発の事故対策統合本部事務局長の細野豪志首相補佐官が海水注入の中断問題について語った。
−−原子力安全委員会の班目春樹委員長は「海水注入で再臨界の可能性があるとは指摘していない」と反論した
「(3月12日)午後6時からの会議で、東電役員が『水素爆発で現場が混乱し、1時間半は注水できない』と言ったので、その間、ホウ酸注入や海水による影響を検討するよう菅直人首相が指示した」
「19時40分に再度集まり、ホウ酸を入れることで作業を進めた。同4分から25分に、東電が試験注入をしていた情報はなかった」
−−菅首相は「再臨界の危険性はないのか」と発言したか
「首相が再臨界を心配していたのは事実だ」
−−それは班目氏の意見を受けてか
「そう記憶している」
−−班目氏は「あり得ない」と反論している
「班目氏が言った記憶はあるが、確認する必要がある」
−−東電はなぜ注水を止めたのか
「それが最終的にどう影響したかなどは検証し、責任を議論してもよい。ただ、検証で現場の作業が止まるのが心配だ」
福島1号機、ベント判断に遅れの可能性
2011.5.23 00:25 東日本大震災の直後、東京電力福島第1原発1号機で、放射性物質を含む蒸気の外部への放出作業「ベント」の判断が遅れ、水素爆発を招いた可能性があることが22日、分かった。爆発の約13時間前には運転手順書にあるベントを行う圧力近くまで達していた。 東電によると、格納容器の内部圧力を下げるベントは、使用圧力の上限値(427キロパスカル)の2倍に相当する853キロパスカルに達する前に実施する手順だった。 判明している記録では、3月11日に津波が襲った直後、1号機の原子炉圧力容器内では冷却機能が失われ、翌12日、圧力容器を覆う格納容器の圧力が上昇。午前2時半には840キロパスカルに達していた。 水素爆発が発生した午後3時36分の約13時間前に、ベントを行う条件を満たしていた可能性がある。記録では12日午後2時半にベントの成功が確認されているが、1号機はその約1時間後に爆発した。
九州大の工藤和彦特任教授(原子力工学)は「840キロパスカルは格納容器が破損しかねない圧力だが、電源が失われた上、線量が高くて近づけず、手動でもベントできなかったのではないか」と話している。
| 1 気圧(標準大気圧)(atm)= 1 013.25hPa = 101.325kPa 840kPa=8.4気圧 |
4号機損傷部近くで空気中の放射性物質量を測定 東電
2011.5.23 20:56 東京電力は23日、福島第1原発事故で、水素爆発を起こした4号機の原子炉建屋の損傷部近くで、空気中に放出されている放射性物質の量を測定した。東電は原子炉建屋全体をカバーで覆って空気中への拡散を防ぐことを計画しており、測定データを参考にする方針。1号機ではすでに実施している。
4号機使用済み燃料プール底部の耐震補強工事では、準備作業のため、原子炉建屋2階にある部屋に作業員が入り、足場の組み立てなどを始めた。7月の補強完了を目指す。
また、東電は同日、2号機原子炉建屋内で18日に採取した空気中の放射能濃度について、「作業環境が悪く、信頼できるデータではなかった」として、再測定することを明らかにした。
東電によると、18日に2号機建屋内に入った際、放射線量の測定とともに、空気中の放射能濃度を調べるために空気を採取した。湿度と温度が高く、作業時間が限られた上、特殊な防護服や空気ボンベなどの重装備だったため、測定に十分な量の空気を採取できなかった恐れがあり、東電は「信頼できない」と判断した。近く再測定を行う。
2、3号機も炉心溶融、圧力容器損傷の恐れも 東電がデータ解析公表
2011.5.24 09:37
東京電力は24日、福島第1原発事故の発生当初のデータの解析から、1号機と同様、2、3号機でもメルトダウン(炉心溶融)が起きているとの結果を公表した。原子炉の水位について、計器が示した水位より実際には低い場合、燃料が入っている原子炉圧力容器の損傷が起きたと推定している。 ただ、現在の圧力容器周辺の温度からは、燃料の大部分が圧力容器にあると判断。安定的に冷却を進められており、今後、事故の進展はないとしている。
水位が実際には低い場合は、2号機では自動停止の約101時間後、3号機では約60時間後に大部分の燃料が圧力容器の底に落下したと解析した。
3月11日の東日本大震災後の事故発生当初の原子炉の様子について、残っていたデータなどを基に分析。経済産業省原子力安全・保安院に報告書を提出した。
2、3号機も炉心溶融「燃料の大半は圧力容器内」 東電が解析
2011.5.24 10:36
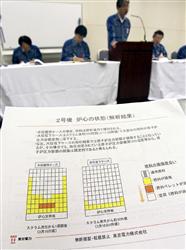
福島第1原発事故で、2号機3号機の炉心溶融を発表する東京電力。水位維持と低下の2つのパターンを想定して解析した、燃料の損傷を示す炉心の状態を発表した。写真は2号機の炉心の状態=5月24日、東京電力本店(撮影・早坂洋祐)
東京電力は24日、福島第1原発2、3号機の地震発生後の炉心状況などを解析した結果、原子炉圧力容器内の冷却水が失われていた場合、2号機は地震から約101時間後の3月15日午後8時ごろ、3号機では約60時間後の同14日午前3時ごろに核燃料の大部分が溶融し、1号機と同様、圧力容器底部に落下し、「炉心溶融(メルトダウン)」していたと発表した。23日に報告書を経済産業省原子力安全・保安院に提出した。
また、1号機については、地震発生から約15時間後に圧力容器が破損したとの解析結果も示した。
東電によると、2、3号機について、原子炉内の水位は低下しながらも一定量を維持、水位計の計測値が信用できる場合と、水位計データは信頼できず実際には冷却水がほとんど失われていた場合の2ケースについて、データ解析を行った。 その結果、両機とも、いずれの場合も水位低下の後に燃料が溶けた状態になった。冷却水が失われていたケースでは、ほぼすべての燃料が圧力容器の底に溶け落ちていたとしている。
東電は「炉心の温度から考えると、圧力容器の損傷は限定的で大きな穴が開いている状況ではない。実際は2つのケースの間にあるのではないか。燃料の大部分は圧力容器内にあると考えられ、継続的な注水で現在は十分冷却できている」としている。
地震発生後から津波によって、すべての交流電源が失われるまでの状況については、「主要機器の破断、冷却水の喪失はなかった」と判断、津波到達まで外部への放射性物質の放出もなかったとした。 また、1号機の原子炉の非常用復水器が、地震発生直後に起動したが約10分後に停止した問題については、炉心温度が急激に低下したため作業員が手動停止したことを認め、東電は「作業手順書に沿った操作で、妥当」と判断した。
東電は今月16日に地震発生当初からの同原発のデータや活動記録を保安院に提出。保安院は、記録に基づき、緊急時の炉心冷却機能の動作状況や、設備の異常が地震と津波のどちらによるものかの評価、電気設備が被害を受けた原因などを報告するよう東電に求めていた。
東電は15日、1号機についても地震翌朝の3月12日午前6時50分ごろに炉心溶融していたとする暫定解析結果を公表している。
2号機貯蔵プールに熱交換器 建屋内作業へ湿度低下目指す
2011.5.25 01:09
東京電力は24日、福島第1原発2号機の燃料貯蔵プールの水を循環冷却させるため、熱交換器を原子炉建屋近くに設置したと発表した。今月中にも稼働させ、1カ月後にはプールの水温を41度程度に下げる。 2号機は高い湿度が作業の妨げとなっており、循環冷却させることで、水蒸気の発生を抑制する。プールの水をポンプで引き込み、冷却して循環させる。
また、東電は1号機と4号機の原子炉建屋上空の放射性物質を初めて計測。国が定める濃度限度の0・01〜0・18倍に当たる放射性物質が検出されたと発表した。
一方、経済産業省原子力安全・保安院は24日、東京電力福島第1原発から流出した放射性物質について、17日の段階で原発専用港の湾内に14兆ベクレル残留しているとの分析結果を公表した。保安院は「ただちに港湾の外に出ていくことはない」としている。
格納容器に7〜10センチの穴か 工程表への影響必至 福島原発1、2号機
2011.5.25 12:42
福島第1原発事故で、メルトダウン(炉心溶融)が起きたとみられる1、2号機では原子炉格納容器に7〜10センチ相当の穴が開くなどの破損があり、高濃度の汚染水が漏れ出た可能性の高いことが25日までに東京電力の解析で分かった。
爆発により破損したとみられていた2号機の圧力抑制プールに加え、燃料のある原子炉圧力容器の外側の格納容器にも破損の可能性が出てきたことで、各号機にたまる高濃度の汚染水の処理がより困難になるのは確実。収束に向けた工程表への影響は避けられない状況になった。
東電は経済産業省原子力安全・保安院に提出した報告書の中で、1号機について、地震から18時間後に直径約3センチ相当の穴が開き蒸気の漏れが発生、50時間後に約7センチに広がったと想定すると、実際に格納容器内で計測された圧力の変動によく合うことを確かめた。
漏れが起きた時刻には、格納容器の温度が設計温度(138度)を大きく超えた約300度以上となっており、気密を保つ部品が高温で壊れた可能性があるとしている。
2号機でも、地震から21時間後に高温などにより約10センチ相当の穴が開いたと想定した。この程度の漏えいがないと、格納容器の圧力が上がりすぎて、測定値と合わなくなる場合があるという。 さらに2号機の格納容器では87時間後に、下部につながる圧力抑制プールが破損したとみられ、圧力が急激に低下した。 ただ東電は、いずれも圧力計などに問題があり、測定値が正しくない可能性もあるとしている。
実際は海水注入停止せず 「注入継続が何より重要」 第1原発所長が独自判断
2011.5.26 17:09
東京電力福島第1原発1号機への海水注入が一時中断したとされた問題で、東京電力は26日、実際には海水注入の停止は行われていなかったと発表した。同原発の吉田昌郎所長が「事故の進展を防止するためには、原子炉への注水の継続が何よりも重要」と判断し、実際に停止は行わなかったという。本店の指示に反し、現場が独自の判断をしていた。指示系統のあり方が問題となるとともに、事故対応をめぐる連携の悪さが改めて浮き彫りとなった。
会見した東電の武藤栄副社長は「これまで、説明してきた中身が、現場が錯(さく)綜(そう)する中で事実と違い、申し訳ない。コミュニケーションの行き違いがあった」と謝罪した。
吉田所長の判断については「技術的には妥当だった」(武藤副社長)とした。吉田所長の処分については今後検討するという。
東電によると、海水注入は3月12日午後7時4分に開始。21分後の午後7時25分に、首相官邸に派遣した東電社員から「首相の了解が得られていない」との連絡が東電本店にあったため、本店と原発でテレビ会議を行い、注入の停止を決定した。しかし、吉田所長はその決定に従わず、独自の判断で注入を続けたという。
東電本店の社員が24日から25日にかけて、状況を再確認するため同原発で吉田所長から事情を聴取し、事実が判明した。吉田所長は「新聞や国会で話題になっており、IAEA(国際原子力機関)の調査団も来ていることから、事故の評価解析は正しい事実に基づいて行われるべきだと考えた」と説明し、事実を明らかにしたという。
東電は21日に同問題の経緯を初めて明らかにした際、12日午後8時20分に海水注入を再開したと説明していた。この点について東電は「当時、発電所からそういった報告があったが、適切な報告ではなかった」と発表内容を訂正した。東電は21日に問題の経緯を明らかにした時点で、吉田所長からの事情聴取は行っていなかったという。
同問題をめぐっては、海水注入が原子炉を冷却するための唯一の方法だったため、菅直人首相の言動を受け、東電が海水注入を停止した点などが、国会でも問題視されていた。
移送先の水位低下 連絡通路に流出、建屋外にも?
2011.5.26 21:41 東京電力は26日、福島第1原発3号機から汚染水を移送している「集中廃棄物処理施設」の建屋の水位が約5センチ低下、別の建屋をつなぐ連絡通路に汚染水が流出し、深さ約2メートルの水がたまっているのが見つかったと発表した。建屋外に漏れている可能性もあり、東電は建屋周辺の地下水の採取地点を増やし、汚染水が環境中に漏出していないか監視を強化する。 東電によると、流出が確認されたのは2号機のたまり水の移送先である建屋との連絡通路。この通路は外部に水を漏らさないための止水工事をしていない。
汚染水処理、綱渡り 移送先で漏水、通路に水たまり
2011.5.27 07:37 東京電力は26日、福島第1原発3号機から汚染水を移送している「集中廃棄物処理施設」の建屋の水位が約5センチ低下、別の建屋をつなぐ連絡通路に汚染水が流出し、深さ約2メートルの水がたまっているのが見つかったと発表した。建屋外に漏れている可能性もあり、東電は建屋周辺の地下水の採取地点を増やし、汚染水が環境中に漏出していないか監視を強化する。 東電によると、流出が確認されたのは2号機のたまり水の移送先である建屋との連絡通路。この通路は外部に水を漏らさないための止水工事をしていない。
福島第1原発の汚染水問題で、移送先施設の水位低下が判明、漏水の疑いが浮上したことで処理計画は見直しを迫られる可能性も出てきた。東京電力は、ほぼ満杯となった同施設に追加で5千トンを移せるとするが、実際に漏水していれば移送は断念せざるを得ない。汚染水の浄化システムが稼働するのは6月中旬。増え続ける汚染水の処理は、3週間近くも綱渡り状態が続くことになる。 汚染水は1〜4号機の原子炉やタービン建屋などの地下に計約9万8500トンあると推計されている。原子炉を冷やすために注入された水が漏れだしていると考えられており、「冷却水を入れれば、入れただけ、汚染水が増える」(東電)状況だ。
汚染水をそのまま放置すれば海へ流出する恐れがある。そのため、東電は放射線量が高い2号機と3号機の汚染水を優先して集中廃棄物処理施設に移送。汚染水の浄化システムで放射性物質を取り除き、タンクや静岡市から譲り受けた人工浮島「メガフロート」などに貯蔵する計画だった。
だが、ここへきて誤算が生じ始めた。汚染水の浄化システムの稼働時期が設置工事などの遅れで6月上旬から中旬にずれ込んだうえ、3号機の原子炉温度が5月上旬から上昇。予定よりも多くの水を注入する必要に迫られ、それに伴って汚染水も増加したのだ。 その結果、東電が想定していた6月上旬よりも早く貯水施設が満杯に近づき、3号機分の移送をいったん停止する事態になったところへ、今回の「漏水疑惑」が追い打ちをかけた形だ。 東電は「水位低下の原因が分かるまで水の移送はできない」と説明しており、他に移送先の候補がない現状では、汚染水は原子炉建屋やタービン建屋の地下にため続けることになる。
こうした事態に、北海道大の奈良林直教授(原子炉工学)は「冷却のためには炉心注水は止められない。東電も移送先が満杯になるのは想定していたはずで、備えが遅い」と、見通しの甘さを指摘する。東電はタービン建屋などの大量の汚染水を浄化し、原子炉に入れて冷却に再利用する「循環注水冷却」を事態の収束に向けた工程表に盛り込んだが、この冷却方式は汚染水処理が順調に進むことが前提。実際に漏水が判明すれば、工程表への影響は避けられそうにない。(原子力取材班)
福島第1原発、非公表データが存在
2011.5.27 17:21 枝野幸男官房長官は27日午後の記者会見で、放射線量を計測するために東京電力福島第1原発周辺に設置されているモニタリングポストのデータの一部で、これまで非公表のものが存在したことを明らかにした。 また、事故対策統合本部の事務局長である細野豪志首相補佐官に対し、「直ちに内容を精査、整理して公表するように厳しく東電に指摘し、調査するようにと指示した」と述べた。
枝野氏は「こうしたことが繰り返されると国民から信用されない。原発事故と同じぐらい深刻だと受け止めている」と東電を批判した。
水素爆発の3号機を視察 IAEA、福島第1原発に
2011.5.27 18:42 福島第1原発事故の原因解明を進めるため、来日中の国際原子力機関(IAEA、本部ウィーン)の調査団が27日、現地入りして1〜4号機の視察や事故状況の説明を受けた。 東京電力によると、同日午前に現地に入ったウェイトマン団長らは防護服を着用。第1原発の吉田昌郎所長から写真や図面をもとに事故状況や津波の被害について説明を受けた。その後、調査団は全面マスクを装着し、水素爆発で原子炉建屋が大きく損壊した3号機の外観や、非常用のディーゼル発電機、作業拠点となっている免震重要棟などを視察した。 調査団は28日に東京に戻り、6月1日までに報告書の素案を作成する予定。
水素爆発後も原子炉建屋「安全」と東電 福島第1原発1、4号機
2011.5.28 12:27 東京電力は28日、福島第1原発1、4号機の原子炉建屋について、3月11日に発生した大地震とその後に発生した水素爆発の後も、十分な耐震安全性を維持しているとの評価結果を発表した。 第1原発の原子炉建屋は地震後、原子炉や使用済み燃料プールの冷却ができなくなり、影響で発生した水素が爆発。1〜4号機で原子炉建屋の壁などが大きく破損した。国は東電に対し4月13日、耐震安全性の評価と、耐震補強工事の検討を指示していた。 東電によると、現存する構造物のデータを基にシミュレーションを実施したところ、想定した最大の揺れの強さ(基準地震動)でも大きく壊れないことが分かった。東電は「さらなる安全性を確保するため、補強工事も行う」としている。 2、3号機の原子炉建屋については「評価中」としている。
3000マイクロシーベルト超の高線量も 地震直後の未公開値発表
2011.5.28 13:25 東京電力は28日、福島第1原発敷地内で、3月11日の地震発生後から同月15日までに測定していた未公表の放射線量データを発表した。公表済みの10分ごとの測定値の間を埋める2分ごとの値などが含まれ、最高線量は3月15日午前8時55分の正門付近の毎時3509・0マイクロシーベルト。毎時3509マイクロシーベルトは、その場に20分いるだけで一般人の年間被ばく限度を超える放射線量。 東電によると測定時に紙に記録したが、その後紛失したものもあり、既に報告していた経済産業省原子力安全・保安院から取り寄せたり社内で見つけたりしたとしていた。だが28日の会見では紛失はなかったと説明を変更した。公表済み最高観測値である15日午前9時の毎時1万1930マイクロシーベルトを超えるものはなかった。
東電の情報公開をめぐっては26日、1号機で地震翌日に海水注入を一時中断していたとするそれまでの発表を翻し、所長の独断で続いていたことも判明するなど、混乱が続いている。
「柏の放射線 大丈夫?」 小学生校外学習 不安募る保護者
2011.5.28 21:57 東京都文京区が区内の小学4、5年生を対象に行っている千葉県柏市での校外学習について、保護者から安全性に関する問い合わせが相次いでいる。柏市は福島第1原発から約200キロ離れているが、都内などと比べ高い放射線量が検出されているためだ。ただ、健康を害するような数値ではなく、区教委は保護者あての通知を各校に配布し、不安の解消に努めている。 文京区では例年、4月中旬から2泊3日の日程で、飯盒(はんごう)炊飯や地元農家の見学など屋外活動中心の校外学習を柏市内の施設で実施。今年は原発事故の影響で延期されていたが、区が今月、順次実施する方針を決めた。 その後、保護者から区教委に「放射線は大丈夫か」「現地での食事の産地は」といった問い合わせが続出。原子力の研究者らと独自に全国の放射線量を計測、ホームページで公表している近畿大原子力研究所の若林源一郎講師(放射線安全学)にも、女性から柏市の放射線量データを求める電話があったという。 若林講師らの計測結果によると、例えば柏市の5月14〜20日の最大放射線量は毎時0・344マイクロシーベルトで、0・130マイクロシーベルトの文京区や原発により近い茨城、栃木両県の自治体と比べてもやや高い線量を記録。東京大学の調査でも同様の結果が出ており、インターネットへの書き込みが相次いだことなどから保護者が不安を募らせたようだ。 ただ、国の屋外活動制限基準(3・8マイクロシーベルト)は大きく下回っており、若林講師は「健康に影響が出る数値ではない。ラドン温泉に行った程度」と指摘。「実際の健康被害より、健康被害を心配する心的ストレスの方が体に与える影響がはるかに大きい。正しい情報を把握したうえで冷静に対処して」と呼びかけている。
5号機で冷却ポンプ停止 原子炉の温度上昇 福島第1原発
2011.5.29 11:17 東京電力は29日、冷温停止中の福島第1原発5号機で、原子炉や使用済み燃料プールの冷却系ポンプが停止するトラブルがあり、原子炉などの温度が上昇していると発表した。予備ポンプに切り替える復旧作業を急いでいる。 東電によると、28日午後9時ごろ、敷地内をパトロール中の作業員がポンプの停止を見つけた。この段階で原子炉の温度は約68度、プールは約41度だったが、復旧作業を開始した29日午前8時すぎにはそれぞれ約87度、約44度まで上昇していた。
2号機付近の海水中濃度上昇 シルトフェンス内
2011.5.29 22:10 経済産業省原子力安全・保安院は29日、福島第1原発2号機の取水口付近の海から採取した水の分析で、放射性物質の濃度が27日から28日にかけて数倍に上昇したと明らかにした。西山英彦審議官は「これまで出たものが(海中で)舞い上がっているか、新しい(漏えいなどの)現象か分からない。データを見ていく必要がある」と話した。 保安院によると、放射性物質の拡散を抑えるため取水口前に設置したカーテン状の「シルトフェンス」の内側で、放射性のヨウ素とセシウムの濃度が、27日は法令の濃度限度の19〜130倍だったが、28日には48〜600倍になった。
また東京電力は、26日に測定した2号機の原子炉建屋の放射線量は、建屋の北側と西側で毎時20ミリシーベルト前後と発表した。空気中の放射性物質の濃度は建屋北東で、放射線業務従事者が作業してよいとされる限度の40〜110倍。建屋内の湿度は99・9%と依然高かった。
福島第1、年内収束は絶望 東電幹部見解、循環冷却構築に時間
2011.5.30 07:47 福島第1原発事故の収束に向けた工程表について、東京電力が「年内の収束は不可能」との見方を強めていることが29日、複数の東電幹部の証言で分かった。 1〜3号機でメルトダウン(炉心溶融)が起き、原子炉圧力容器の破損が明らかになったことで、東電幹部は「作業に大きな遅れが出るだろう」としている。 東電は4月17日に「6〜9カ月で原子炉を冷温停止状態にする」との工程表を公表、1号機の炉心溶融が発覚した後の5月17日にも工程表の見直しはないとしていた。 東電幹部の一人は「9カ月という期限はあくまで努力目標だ」としており、原子炉を安定状態に持ち込んだ後に想定していた政府による原発周辺住民の避難見直し時期についても影響が出そうだ。
東電は5月初旬まで、原子炉格納容器に水を満たし燃料が入った内側の圧力容器ごと冷やす「冠水」に向けた作業を続けていたが、12日に1号機の炉心溶融と圧力容器の損傷が明らかになり、冠水を断念。原子炉建屋にたまった大量の汚染水を再利用する「循環注水冷却」という新たな方法で原子炉を冷却する方針に切り替えた。 1号機では格納容器から汚染水が漏れていることも判明しているため、東電の技術系幹部は「まずどこから漏れているか突き止め、塞がなくてはならない。損傷程度が分からないと、その作業にどれほどの時間がかかるのかすら分からない」としている。
さらにこの幹部は「継続的に大量の水を循環させて冷却するシステムを構築しなければならず、技術的に見て想定より1〜2カ月程度余計にかかる」としている。 別の幹部は「1〜3号機の収束作業は同時進行できていない。1基ごとに同様の遅れが生じると、9カ月という期限もギリギリだ。作業員には申し訳ないが、正月返上で収束にあたってもらうことになる」と話している。
SPEEDIを初公開 放射性物質拡散予測システム
2011.5.30 19:44

「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)」の出力図形表示用端末=30日午後、東京都文京区(代表撮影)
原子力安全技術センター(東京都文京区)は30日、放射性物質の拡散予測システム「SPEEDI(スピーディ)」のオペレーションルームを初公開した。
原子力事故発生時、放射性物質放出源の情報や気象などのデータを基に、サーバー約50台で構成する大型コンピューターが、放射性物質の拡散モデルを即座にシミュレーションする。
東京電力福島第1原発事故後は、炉心の状態が不明のため原子力安全委員会が環境モニタリングから逆算した推定データを使うなどして延べ1万枚以上の拡散予測図を出力したが、公開の遅れもあり、住民避難に十分活用されなかった。
同センターの恒吉邦秋防災技術部長は「反省すべき点はある。傾向だけでも早く示せばよかった」と話した。 SPEEDIは1979年の米スリーマイル島原発事故を契機に開発され、文部科学省が所管、同センターに運用を委託している。
福島・飯舘村で積算20ミリシーベルト超 文科省測定、原発から33キロ
2011.5.30 13:16 文部科学省は30日、福島第1原発から北西33キロの福島県飯舘村で、3月23日から5月29日までに観測した積算放射線量が20ミリシーベルトを超えたと発表した。文科省は原発から半径20キロ圏外の15地点で積算線量を測定しており、20ミリシーベルトを超えたのは同県浪江町に次いで2地点目。
政府は、1年間の積算被曝(ひばく)線量が20ミリシーベルトに達する恐れのある地域を計画的避難区域に指定、飯舘村や浪江町も含まれる。文科省は、積算線量測定を屋外で継続しており、「屋内で過ごす時間を考慮すると、実際に浴びる放射線量と測定値は異なる」と説明している。
積算線量を測定している15地点のうち、最高値は原発の北西31キロの浪江町で約35ミリシーベルト。次いで飯舘村の約20ミリシーベルトで、ほかは約17〜0・25ミリシーベルトとなっている。
東電、社員2人が被曝250ミリシーベルト超の恐れと発表 甲状腺に放射性ヨウ素
2011.5.30 19:31 東京電力は30日、福島第1原発事故の作業に当たった男性社員2人が、今回の事故対策に限って引き上げられた被(ひ)曝(ばく)線量限度の250ミリシーベルトを超えた恐れがあると発表した。内部被曝線量を詳しく調べ、外部被曝と合わせた線量を確定する。
東電は「結果的に数百ミリシーベルトになるかもしれない。ただ、(放射性物質の排出促進などの)緊急時医療が必要という段階ではない」としている。2人から自覚症状の訴えはなく、30日に放射線医学総合研究所(千葉市)で健康診断を受けたが、問題はないという。
2人は30代と40代で、3、4号機の運転員。23日の測定で、2人の甲状腺に取り込まれた放射性ヨウ素131が7690〜9760ベクレルと、ほかの人に比べ10倍以上多かった。取り込んだ時期が早ければ、被曝線量が総計で250ミリシーベルトを超えている可能性がある。外部被曝は約74〜89ミリシーベルト。 2人は3月11日の地震当日から中央制御室や免震重要棟、屋外などで作業していた。甲状腺への放射性ヨウ素の取り込みを防ぐヨウ素剤を13日に服用していたという。
これまで200ミリシーベルトを超える被曝が判明しているのは、3月24日に3号機タービン建屋の地下で、たまった汚染水に両足を漬けて作業した東電の協力会社の作業員2人で、240・8ミリシーベルトと226・6ミリシーベルト。緊急時作業の被曝線量の上限は100ミリシーベルトだが、厚生労働省は今回の事故に対応する作業員に限り、上限を250ミリシーベルトに引き上げた。
100ミリシーベルトを超えるとがんを発症するリスクが少し高まる可能性があるとの指摘もあり、健康調査が必要になる。
また東電は30日、同原発の建屋や立て坑にたまっている放射性物質を含む汚め染水の水位が、降雨のため上昇していると発表した。
福島第1原発を生中継 東電ホームページで
2011.5.30 22:18 東京電力は30日、福島第1原発のライブ映像の配信を、31日午前10時から同社ホームページで開始すると発表した。
1号機の北西約250メートルの事務本館付近にカメラを設置。1〜4号機の原子炉建屋などをとらえた動画を24時間流す。ただし、通信機器を経由するため、現地の実際の動きと映像とは約30秒の時間差がある。
雨で汚染水の水位上昇 1号機原子炉建屋で20センチ
2011.5.30 23:26 東京電力は30日、福島第1原発の建屋や立て坑にたまった放射性物質を含む汚染水の水位が、降雨のため上昇したと発表した。福島地方気象台によると、同原発周辺では同日も断続的に雨が降った。
1号機原子炉建屋の地下では、原子炉に注入した水の漏洩(ろうえい)に雨水が加わり、たまり水の水位が29日午前7時からの24時間で約20センチ上昇。1〜4号機のタービン建屋や立て坑でも、29日午後5時からの14時間で水位が約2〜4センチ上昇した。強い雨に備え、東電は建屋の出入り口に土嚢(どのう)を積むなどの対策を取った。
浄化が必要な汚染水の量が増えたが、東電は「処理量が少し増えるが、工程が1カ月も2カ月も延びるということではない」としている。
福島第1原発で海水浄化装置を導入 東電
2011.5.30 23:58 福島第1原発事故で東京電力は30日、放射性物質で汚染された海水を浄化する装置を設置すると発表した。6月1日に通水試験を行い、問題がなければそのまま稼働させる。 浄化装置はセシウムの除去が目的で、一辺約2.3メートルの立方体。内部には放射性物質を吸着する鉱物ゼオライトが詰められており、ポンプでくみ上げた海水を通し、上澄みを海に戻す。 1時間あたり約30トンの海水処理が可能で、東電のテストでは1回で約30%のセシウムが除去できたという。 装置は2号機と3号機の取水口の中間に設置。事故を受けて東電が新たに設計した特注品で、効果は運転しながら確認する。今後、増設も検討している。
津波15メートル超で「炉心損傷」 経産省所管法人は「想定外」を想定
2011.5.31 00:31 原発の安全研究に取り組む独立行政法人「原子力安全基盤機構(JNES)」が平成19年以降、津波被害を想定した研究報告をまとめていたにもかかわらず、所管する経済産業省や東京電力が具対策を講じていなかったことが30日、分かった。東電福島第1原発の事故は、ほぼ研究報告通りの展開をたどっており、国や東電が「想定外」と主張する津波の波高についても想定。15メートル超の津波を受けた場合の炉心損傷確率を「ほぼ100%」としていた。
「わが国の原発は、いずれも海岸線に設置されており、地震発生に伴い津波が到来した際には、原発に対して何らかの影響を及ぼし、炉心損傷が発生する可能性が考えられる」 JNESが20年8月にまとめた報告書には、津波被害の項目の冒頭にこう記され、福島第1原発で起きた津波被害を起因とする炉心損傷の可能性を明確に指摘していた。 東電によると、福島第1原発は、津波の影響で、タービン建屋の地下にある非常用ディーゼル発電機が水没して故障。同発電機用の軽油タンクも流されるなどして冷却系の電源や機能がすべて失われた結果、炉心溶融や水素爆発が起き、放射能漏れにつながった。
報告書では、これら実際に起きた具体的な被害をすべて想定しており、結論として「全電源が喪失し炉心損傷に至る可能性がある」と警鐘を鳴らしていた。 22年12月の報告書では、3〜23メートルまでの津波の波高を想定した危険性を検討。海面から高さ13メートルの防波堤がない場合は7メートル超、ある場合でも15メートル超の津波が来た場合、炉心損傷に至る可能性は「ほぼ100%」と分析していた。
福島第1原発の津波対策での想定は波高5・7メートルで、実際の津波は約15メートルだったため、国や東電は「想定外」と主張していた。
JNES広報室は、研究目的について「原発の設計基準を上回る地震対策について国を支援するため」と説明するが、報告書は経産省に直接提出することはなく、ホームページで一般に公表するだけ。研究のあり方も問われそうだ。
日本システム安全研究所の吉岡律夫代表は「国と東電は想定外と主張しているが、報告書を見れば想定外とは言えない。報告に基づき十分な対策を講じていれば、今回の事故は防げた」と指摘している。 原発の津波対策をめぐっては、国の原子力安全委員会が18年、「耐震設計審査指針」を改定した際、津波についても「発生する可能性があると想定される」レベルに備えるよう要求。電力各社は安全性の再評価に着手していたが、耐震対策を優先させ、津波対策は後回しになっていたとされる。
2号機プールを本格冷却へ 東電、6月に向け試運転
2011.5.31 09:49 東京電力は31日、福島第1原発2号機の原子炉建屋にある使用済み燃料プールの水を循環させながら、効率的に熱を取り除く新たな冷却システムの運転に向け、準備を進めた。部分的に試運転しながら配管の水漏れなどを確認しており、6月初めに本格稼働する。
2号機ではプールの熱で生じた蒸気が天井が残る建屋内にこもり、原子炉を含めた収束作業の妨げになっている。これまでは蒸発した水を補う形で配管を通じて断続的に注水していたが、新たなシステムでは常時循環させた水から空冷式の装置で熱を取り除き、作業環境の改善も目指す。
東電が経済産業省原子力安全・保安院に提出した計画では、本格稼働から1日半でプールの水を約65度まで、1カ月で約40度まで下げて安定冷却できるとしている。 東電は建屋が損壊した1、3、4号機でも、同様の冷却システムの構築を予定する。
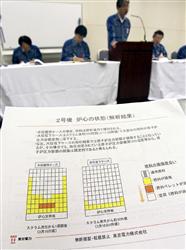 福島第1原発事故で、2号機3号機の炉心溶融を発表する東京電力。水位維持と低下の2つのパターンを想定して解析した、燃料の損傷を示す炉心の状態を発表した。写真は2号機の炉心の状態=5月24日、東京電力本店(撮影・早坂洋祐)
福島第1原発事故で、2号機3号機の炉心溶融を発表する東京電力。水位維持と低下の2つのパターンを想定して解析した、燃料の損傷を示す炉心の状態を発表した。写真は2号機の炉心の状態=5月24日、東京電力本店(撮影・早坂洋祐)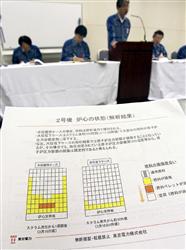 福島第1原発事故で、2号機3号機の炉心溶融を発表する東京電力。水位維持と低下の2つのパターンを想定して解析した、燃料の損傷を示す炉心の状態を発表した。写真は2号機の炉心の状態=5月24日、東京電力本店(撮影・早坂洋祐)
福島第1原発事故で、2号機3号機の炉心溶融を発表する東京電力。水位維持と低下の2つのパターンを想定して解析した、燃料の損傷を示す炉心の状態を発表した。写真は2号機の炉心の状態=5月24日、東京電力本店(撮影・早坂洋祐)