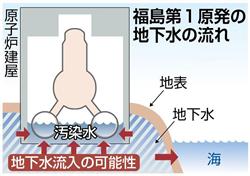2号機再び100度超に「全体としては安定」
2011.9.29 10:55
東京電力は29日、一時は100度を下回った福島第1原発2号機の原子炉圧力容器下部の温度が、再び100度を超えたと発表した。
28日に1〜3号機すべてで100度を切り、冷温停止状態の条件の一つをクリアしたばかりだった。東電は「温度は上下しているが、全体としては安定した状態だ」としている。 東電によると、2号機は28日午後5時に99・4度となったものの、午後11時には100・7度に上昇。29日午前5時には100・0度になった。 冷温停止をめぐっては、細野豪志原発事故担当相が年内達成を目指すと表明。その条件に、圧力容器下部が100度以下になり、放出される放射性物質が抑制できた状態などを挙げている。
放射性物質除染:1〜5ミリシーベルトでも国負担
毎日新聞 2011年9月29日 22時34分
東京電力福島第1原発事故による放射性物質の除染について、細野豪志環境・原発事故担当相は29日、国が対象として指定しない場所についても、年間追加被ばく量が1〜5ミリシーベルトの場所で自治体が除染を実施した場合は、国が予算を負担する考えを示した。
環境省は今月27日、国が指定して除染する対象地域について、事故に伴う被ばく量が年5ミリシーベルト以上の地域と、年1〜5ミリシーベルトでも局所的に線量が高い地域とする方針を明らかにしている。
この方針について福島県市長会は29日、復興対策現地本部(福島市)に、「県民の心情を全く理解していないもので到底納得できない」とする抗議文を提出。同市長会は5ミリシーベルト未満の地域の除染は基本的に自治体負担とする方針と解釈し、撤回を求めていた。
同省によると、局所的に線量が高い地域の除染費用は、政府が除染に使用することを決めた、11年度第2次補正予算の予備費から52億円を充てることを決めている。年1〜5ミリシーベルトの場所は、11年度第3次補正予算で百数十億円を計上する予定だ。
細野環境・原発事故担当相は除染方法について「市町村が適切と思う形でやっていただき、なるべく要望に沿う形で予算を執行していきたい」と話した。
運転手順書、役に立たず「2号機では爆発なし」東電社内調査
2011.10.2 11:26
東京電力福島第1原発事故で、過酷事故などに対応する「運転操作手順書」が役に立たなかったとする報告書を東電の社内事故調査委員会がまとめたことが2日、分かった。非常用ディーゼル発電機などが動くことを前提としていたが全て動かず、事故対応に生かせなかった。また2号機の圧力抑制プール付近では水素爆発はなかったと従来と異なる判断を示した。
報告書によると、2号機と4号機で大きな爆発音があり、2号機では格納容器につながる圧力抑制プールの圧力が低下、4号機では原子炉建屋最上階が損傷していることが確認された。
その後、第1原発敷地内の仮設の地震計が震動を計測していることが判明。爆発による震動は1回だけで4号機での爆発だったとし「2号機の圧力抑制プールの圧力指示値が低下したため、爆発的事象が発生した可能性があると誤って認識した」と結論づけた。
甲状腺機能、10人が変化 福島の子供 信州大病院調査
2011.10.4 10:19 長野県松本市の認定NPO法人「日本チェルノブイリ連帯基金」と信州大病院が福島県内の子供130人を対象に実施した健康調査で、甲状腺ホルモンが基準値を下回るなど10人の甲状腺機能に変化がみられたことが4日、同NPOへの取材で分かった。
同NPOによると、福島第1原発事故との関連ははっきりしない。 健康調査は7月末から8月末にかけて実施。原発事故で福島県から避難し、長野県茅野市に短期滞在していた当時0歳から16歳の子供が医師の問診と、血液、尿の検査を受けた。 甲状腺は成長に関する甲状腺ホルモンなどを分泌。子供は大人よりも放射性ヨウ素が集まりやすく、蓄積すると甲状腺機能低下症や甲状腺がんになる可能性が高まる。